

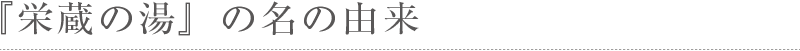
源平盛衰のむかしのむかしおよそ850年前のむかし
栄蔵という僧が小島に小屋を建てて修行をしていました。
その栄蔵を尋ねて来た西行法師がその質素な暮らしぶりに感じ入り
裸島にたとえて詠ったという歌が残っています。
「大田尻衣はなきか裸島沖吹く風は身にはしまぬか」これに対して栄蔵が次のように反歌したといわれています。
「朝な夕な浪のぬれ衣着るものを、裸島とはなに名づくらん」
栄蔵小屋は黄門さまゆかりの地でもあります。
今からおよそ3百年前の元禄十年はるばる丹波国小口(京都府亀岡市)からやって来た、国学者の安藤朴翁の旅日記『ひたち帯』を読んでみると、当時七十歳になった黄門様が栄蔵小屋があった小島に橋を架けさせたとあり、それを渡った時の朴翁の驚きと興奮した様子が書かれています。
「川尻の浜などをすぎて栄蔵小屋といふ嶋山を見る。 この嶋山はむかしは田尻村の山つづきたりしが、 あらき浪風にいつとなく崩れたへておのづから嶋となれりとぞ。 西山公(黄門様のこと)の好事にて、 こなたの岸より橋をかけて渡り通ふに、 橋の下四、五丈もやあるらん。 蒼浪たたへていとすさまじく、股ふるひ、 あなうら(足裏)しじ(ちじ)まる心地ぞする。 嶋はみないはほにして、まわり六、七町もあるべき・・・」
この小島はいつの頃からか海中に没して その姿を消してしまいましたが、 江戸幕府が元禄十五年に作成した「常陸国絵図」にその橋が小さく描かれているのが見えます。
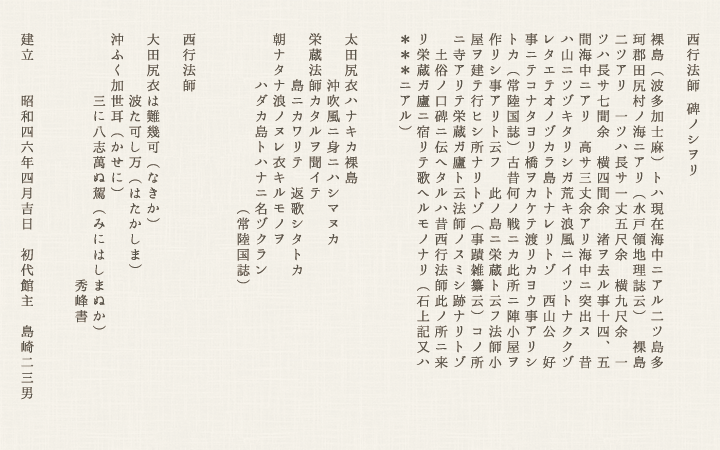

西行法師の石碑